今回の投稿が遅れた理由は二つ。一つは3月31日(日)のイースターに向かう聖週Holy weekをひとまとまりとして記載したかったから、もう一つは、Fauréのレクイエムに引っかかってしまい、にわかリサーチをすることになってしまったから。まずは二番目から。ただし、素人の「観想」。聖週については次回。
~~~
木曜日に、現代最もよく知られた教会音楽作曲家であるJohn Rutterが指揮する Gaburiel Fauré(1845-1925)のレクイエムと、ラター自身作曲のレクイエムの演奏会が、大学公式行事のための Sheldonean Theater を会場に行われた。演奏はOxford Philharmonic OrchestraとMerton College Choir。今回は、ラターのレクイエムには触れない。フォーレは、オーケストラの大型化という時代の流れに逆らい作曲した。このレクイエムは3回にわたって(1888年、1893年、1990年)書き改められ、現代の演奏の多くは第3稿の大きな編成のオーケストラ版。しかしラターは、第3稿はフォーレ自身の音楽の考え方と異なる、弟子による改編という立場から、フォーレ自身の手書き譜が失われている第2稿(1893年版)の校訂をする。ラター版は1984年にOxford University Pressより出版された。ラター版は2010年に彼が主催するCambridge SingersによってCDになっている。音楽学的にラター版への批判もあるが、小規模の弦楽器とホルンそしてオルガンの演奏は、弦楽器一つ一つの音が伝わってくる。
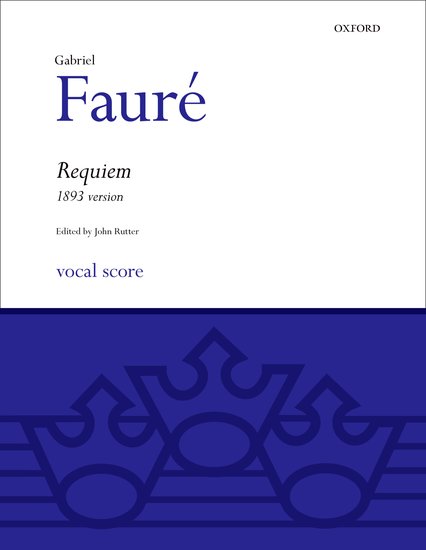

フォーレが小規模の演奏を好んだ理由は、演奏会用であるよりは典礼的でありたい、という思いがあったかららしい。全曲を通じて、それぞれのパートはそれほど大きく揺れることない穏やかなメロディー(時には同じ音程のまま)。祈りを唱えているよう。しかしそれでいながら和声の変革期の作曲家としてのフォーレによる色合いの移り変わりがとても美しい。調性の変化を語る言葉を習得していない自分には、その美しさを表現する言葉がなくもどかしい。印象に基づき語れることを語るとすれば、何かが「無い」こと、そして「有る」こと。
まずは、モーツアルトやヴェルディのレクイエムの中でとても大きな曲である「Dies irae 怒りの日 」そして「裁き」についての言及がフォーレのレクイエムにはない。その意味で、死せる者の安らぎを願うことに焦点があって、生きている者への訓戒的な要素はない。ただ、Dies irae(典礼的にはSequentia)の最後「Pie Jesu慈しみのイエス」は独立の曲としてフォーレのレクイエムの中心に位置している。
第2に、2曲目Offertoireの大部分におけるソプラノの不在。バリトンソロの後、曲の最後にソプラノを聴く時、心の広がりを感じる。また2曲目には神学的にとても重要なフォーレの考え方が込められている。典礼文の 「libera animas omunium fidelium defuntorum 全ての信仰深い 死者の魂をお救いください」の斜字部分が省略されている。フォーレの歌う死者の魂の平安に、キリスト教信仰は前提とされていない。そしてソプラノと共に、典礼文にはない ”Amen どうかそのようになりますように” が歌われる。
第3に、1曲目Introit et Kyrie、2曲目Offertoireにおけるヴァイオリンの不在。3曲目Sanctusになって、女声・男性の高音の掛け合いが賛美をしている上を天使が舞うように、ヴァイオリンのソロが初めて登場する。アルト&テノールそしてビオラ&チェロが人の祈りを歌い、ソプラノそして弦楽器におけるソプラノであるヴァイオリンが、天と地とを繋いでいる。バリトンソロは、人間の切実な願いを歌う。6曲目 Libera me は、裁きについて語るがテーマはそこから解かれること。そこには、全ての想いを込めての願いがある。(なお、第2バチカン公会議以降、教会の死者のための典礼式文には、Dies iraeとLibera me は含まれていない。)
7曲目 In paradisum は、モーツアルトやヴェルディのレクイエムには含まれていない。フォーレの神学は「慈しみのイエス」によって「赦され」「楽園に導かれる」ことを歌う。作曲家としてのフォーレを特徴づける複雑なハーモニーとその目眩く変化は、それが決して単純なことではないと語るが、それら全ては穏やかで美しい。そして論理ではなく、より感覚的なことに中心があるように思える。フォーレを深く知ろうとする時に大切な研究者は、ウラジミール・ジャンケレヴィッチ Vladimir Jankélévitch(1903-1985)。「死」「赦し」をめぐっての多くの著書のあるフランスの哲学者で、死の一人称・二人称・三人称の概念を提唱し、死生学の研究には重要。同時に、音楽学をめぐる哲学者としても注目される。『音楽と筆舌に尽くせないもの (ポリロゴス叢書) 』(国文社: 1995)、『ドビュッシー 改訂新版: 生と死の音楽』(青土社: 1999)、『リスト ヴィルトゥオーゾの冒険』(春秋社: 2001)『フォーレ: 音楽から沈黙へ 言葉では言い表し得ないもの…』(新評論: 2006)、『ラヴェル』(白水社: 2016)、『夜の音楽 ショパン・フォーレ・サティ -ロマン派から現代へ』(シンフォニア: 2019)など近年翻訳が相次いでいる。「語り得ないもの」「生成しつつあるもの」が彼のテーマ。
なぜラターはフォーレのレクイエムの校訂をしなければならなかったのか。フォーレの姿勢の中に、何か似たものを感じたのではないか。ラターは自身のホームページで The Vatican’s Pontifical Council for Culture における講演(2020)を紹介しており、その中で「自分は宗教的な人間ではないが、音楽の神秘には触れており従って同様に信仰の神秘にも触れている」という。ジャンケレヴィッチも音楽の「言葉では言い表せなさineffability」について論ずる。フォーレが、ラターが、そしてジャンケレヴィッチが、言葉でなく表現しようとしたものの入り口に触れた気がしている。ラターは、「[宗教音楽は]、信仰者と非信仰者がユニークでスピリチュアルな何かを分かち合いーそして合意できるー出会いの場」であるという。[https://johnrutter.com/latest-blog/church-and-composers-words-and-sounds ] 。自らのその言葉に従うべく、彼は 2022年に A Ukrainian Prayer を作曲する。楽譜は、名前を登録し無料でダウンロードできる[https://johnrutter.com/news-features/prayer-for-ukraine]。自由に譜面を手にし、自由に演奏し、自由に発信してください、とのこと。
実はカンタベリー大主教が日本を訪問する時に合わせ来日をお願いするため、John Rutterにメールを出したことがある。丁寧にお断りをいただいた。その頃は、多くの彼の曲を桃山学院大学の聖歌隊で演奏する中で、穏やかな人柄を想像していた。しかし今回彼の指揮を見て、とてもエネルギッシュで、しっかりと自己主張をし引っ張ってゆくタイプの方のように感じた。フォーレについて、ラターについて、ジャンケレヴィッチについて、人生の第4期のテーマの一つとして考えてゆきたい。


~~~
以下、毎回のお願い:バックグラウンド・リサーチが不十分なものも掲載します。限られた体験に基づく主観的な記述が中心となります。引用等はお控えください。また、このブログ記事は、学びの途上の記録であり、それぞれのテーマについて伊藤の最終的な見解でないこともご理解ください。Blogの中では個人名は、原則 First Name で記すことにしました。あくまでも伊藤の経験の呟きであり、相手について記述する意図はありません。
伊藤高章 t.d.ito@sacra.or.jp
